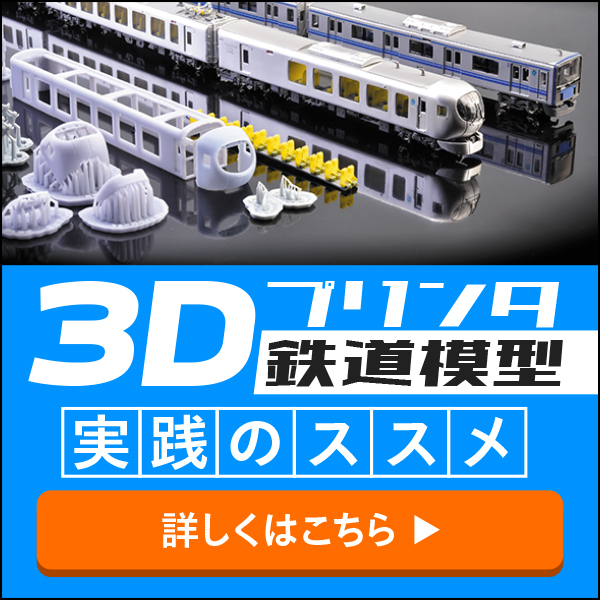■代表的な素材の使い方
植物系表現素材も地表に接着剤を塗布してから素材を貼り付けていくという単純な作業となります。ターフなど粉末系の素材であればそのまま地表に定着してくれますが、フォーリッジなど大粒のスポンジ素材は弾性があるので、しっかり押し付けてあげないと特に傾斜面では乾燥中に剥がれ落ちてしまいます。 それを防ぐには、モーリンのスーパーフィックスを予めフォーリッジに染み込ませたもので貼り付けると、接着剤の粘性で保持ができ、乾燥後もフォーリッジ自体が硬化してしっかり固着できます。 ここでは、植物系表現素材の中でも使用頻度の高いフォーリッジとフォーリッジクラスタの基本的な使用法を解説します。
- 下地のパウダーを撒いた地表の上に、モーリンのスーパーフィックスを筆で塗布する。
- 使用するフォーリッジは、スーパーフィックス(原液のまま)を染み込ませておく。
- スーパーフィックスが染み込んだフォーリッジを、軽く押し付けるように地表に貼り付けていく。
- 接着剤が乾く前に上からターフを撒くと、細かい葉の表現になる。フォーリッジとは異なる色を使うと、黄緑系なら新芽、茶系なら枯れ葉の表現になる。
- フォーリッジクラスタは、製品状態では固形なので、樹木のサイズに小さくちぎってから使用する。
- フォーリッジと同様、地表にスーパーフィックスを塗布し、染み込ませたものを貼り付ける。ただし、この方法は地形が平坦または傾斜が緩い場所に限られる。
- 崖など急斜面の場合は、「スチのり」 または「発泡スチロール用接着剤」を使用する。接着方法はペタペタと糸を引かせてから圧着する。
- スチのりが乾いたらフォーリッジと同様、スーパーフィックス(またはボンド水溶液)を染み込ませてしっかり固着させる。
■ポロポロ落ちるフォーリッジ…その対策は!?
「地表に接着剤を塗布してから素材を貼り付ける」… 基本的な方法としてはこれは正解です。しかし、接着剤は接合面しか浸透しておらず、表面側には接着効果はありません。上の解説で接着剤(スーパーフィックス)を浸透させたものを使用しているのもそのためで、植物系表現素材は基本的に「接着剤を浸透させて使うもの」と覚えておきましょう。持ち運ぶ機会の多いジオラマでは、運搬時の振動や接触で素材の脱落が発生しやすいので特に注意が必要です。

▲接着剤を塗布した地表にフォーリッジを押し付けながら接着。技法としては正解だが、ここで終えてしまっている例が多い。これだけだと素材が剥れやすい。

▲確実に接着するには上記の解説にあるように予め接着剤を染み込ませるか、最終仕上げ時に後から染み込ませると良い。後者の方法なら既に完成している作品 でも予防策として施工可能だ。
■素材を容器に移して作業効率を上げる!
カラーパウダーやターフなど、粉末系素材製品の多くはビニール小袋でパッケージされており、そのまま開封して指で摘んでパラパラ…。使用後もビニール袋のアタマを丸めて輪ゴムで留めて色々な素材が入った箱に収納…。これでは作業効率が悪く、収納時も振動で素材がこぼれ出す恐れがあります。そこで便利なのが、「調味料ポット」です。
- 粉末系素材の多くはこのビニール小袋でパッ ケージされている。使っていくうちにビニールが裂けてしまうことも。
- 粉末系素材の収納に便利なのが、100円ショップでも販売している「調味料ポット」。用途も同じ粉末なので、使い勝手は砂糖や塩のそれと変わらない。
- 使い方は言うまでもなく各素材ごとに容器に移し替えるだけ。容器は透明なので素材の種類も明確だ。
- 調味料ポットに付属のスプーンがそのまま使えるのも嬉しい。自分で調合した「オリジナルブレンド」を作り貯めるのにも使える。
- 棚に並べればちょっとお洒落なインテリア感覚で収納できる。ただでさえ作業中は部屋に素材が飛散するわ、掃除機の中が詰まるわで、家庭内では肩身の狭い思いをしている情景素材たち。機能性も抜群なお洒落な収納方法なら、家庭内の評価も上がるかも?
これなら素材の種類も明確で、砂糖を使う感覚でスプーンでサラサラっと使えます。また、統一デザインのものを使えば棚にズラッと並べてお洒落に収納できます。お困りの方は是非お試しを!