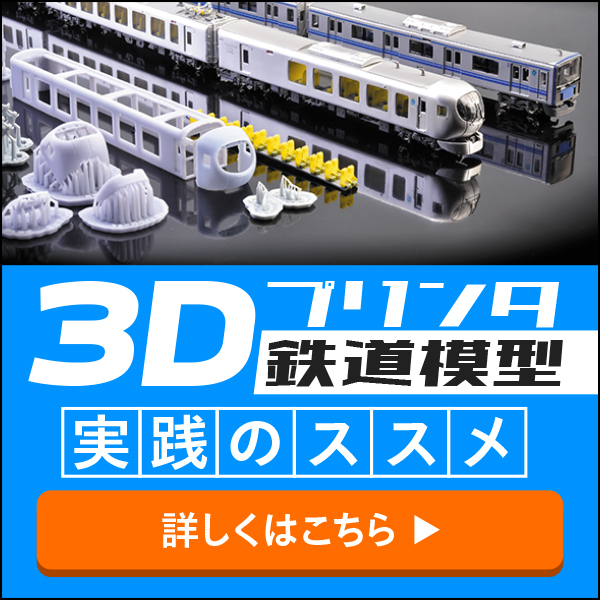私は勝鬨橋が好きだ。この橋が最後に開いたのは1970(昭和45)年のことだという。以来36年、日本を代表する可動橋は“不動橋”となったままだ。数年前、この橋を再び開く計画がある聞き心躍ったが、残念ながら現在のところ実現には至っていない。道路事情もあるだろう、資金の問題もあるだろう。しかし、通る度に思う。この橋が開く姿が見られたどんなに素晴らしいことか。
私は勝鬨橋が好きだ。この橋が最後に開いたのは1970(昭和45)年のことだという。以来36年、日本を代表する可動橋は“不動橋”となったままだ。数年前、この橋を再び開く計画がある聞き心躍ったが、残念ながら現在のところ実現には至っていない。道路事情もあるだろう、資金の問題もあるだろう。しかし、通る度に思う。この橋が開く姿が見られたどんなに素晴らしいことか。鉄道車輌に限らず、動くべきものが動かないのは、寂しい。

話は南国土佐に移る。かつて土電の安芸線に「手結」と書いて「てい」と読む駅があった。市内からの直通電車が今の「ごめん」「いの」と同じく「てい」と書いた行き先板を付けていたということで、その地名が頭の片隅にあったのだが、高知から室戸岬を目指していた時、「手結可動橋」なる標識が目に入り、ここがあの「てい」なのか、と思い出した。今のごめんなはり線だと夜須駅が近い。

 標識にあった可動橋は、船溜まりとなっている古い内港の出入り口に掛けられていた。後で調べたところ、この内港は人工的に掘り込まれた港としては日本最古のものだそうで、景観もなかなかのものである。橋の袂には鉄道のそれを流用したと思われる踏切の警報機と遮断機が備わる。非常ボタンもついているが、押すと橋の上昇が止まるのだろうか。中途半端に止まられても困る気がするが。
標識にあった可動橋は、船溜まりとなっている古い内港の出入り口に掛けられていた。後で調べたところ、この内港は人工的に掘り込まれた港としては日本最古のものだそうで、景観もなかなかのものである。橋の袂には鉄道のそれを流用したと思われる踏切の警報機と遮断機が備わる。非常ボタンもついているが、押すと橋の上昇が止まるのだろうか。中途半端に止まられても困る気がするが。可動橋は、日中おおよそ1時間ごとに開閉するよう、標識に書いてある。つまり、1回開くと1時間通行止めということだ。
とは言え、この日は日曜日。表示の時間が近づいても人の気配が全くない。ひょっとして日曜日は開閉しないのではないか。残念ながらもう時間、“動く可動橋”はお預けか、とその場を離れようとした瞬間、警報機が鳴り出した。

振り返るといつの間にか操作室のデッキにおじさんが赤旗を持って立っている。
「開く!」


遮断機が下りると警報機が止まり、おじさんは中へ。やがて橋が上がり始めた。いざ開くと、予想以上に大きい。これで1時間は通行止めだ。事情を知らない車がやってきて、遮断機の前でしばらく待っていたが、やがて標識を理解したのか、諦めたように引き返していった。もっとも迂回路はあるので、そんなに困ることはない。
勝鬨橋と同じ跳開橋だが、片側のみなので、反対側は遮断管1本を隔てていきなり水路。ちょっと見た目に怖い気もする。
やがて外港で橋が開くのを待っていた漁船がやってきた。小さな漁船だがマストや無線アンテナは可動橋が開かないと通れない高さがある。

後日調べたところ、この可動橋は2002(平成14)年に完成したものだそうだ。観光用でない実用の可動橋を新たに掛けるというのは珍しいのではないだろうか。ちなみに開閉はおおよそ1時間毎と書いたが、よく見ると18時~6時は船舶航行可能と書いてある。つまり夜はひらっきぱなしということのようだ。 →その2
→バックナンバー