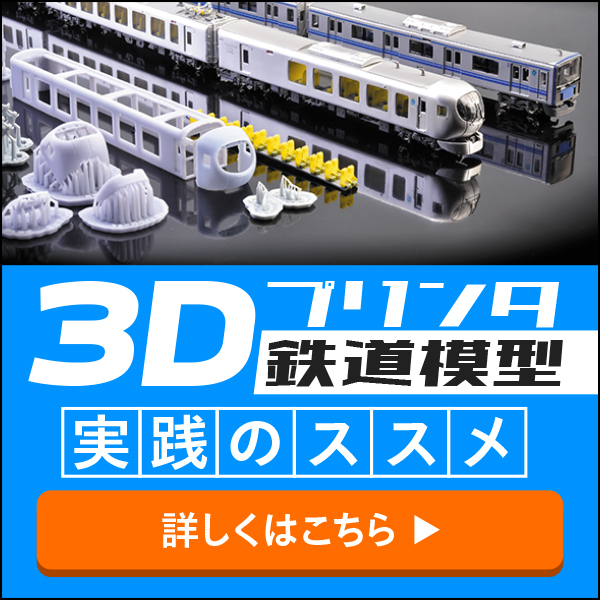text & photo:鉄道ホビダス編集部
この記事の読者の中には、おそらく列車の最前部の常連で、小さいころから所謂「かぶりつき」に親しまれてきたという方もいるでしょう。そのため、列車の運転士が何をしているのかについては興味があったり、完全ではないにせよ、おおよそ把握していたりするのはないでしょうか。
では、車掌についてはどうでしょう。車内放送やドアの開け閉め、ホーム上の安全確認など、おおよそはわかっていても、案外その業務の流れや確認していることはあまり知られていないような印象もあります。
そこで今回は、車掌が日々扱う設備・機器に言及しつつ、「日頃車掌は何をしているのか」ということについて考察していこうと思います。なお、現代の大半の列車の運転形態に鑑み、以下では基本的に電車・気動車列車を想定して話を進めます。
■発車時の動きは?
先ほども少し言及しましたが、車掌はドアの開閉も行っています。当然ながら、ドアが閉まると列車が発車するわけですが、列車を発車させるためには、列車が出発すべき時間になるとともに、当該列車に対して進行を指示する信号が現示されていなければなりません。すなわち、車掌は時間と信号を確認したのちにドアを閉めるわけです。
その際、車掌から必ずしも出発信号機が見えるとは限りません。その際、車掌は出発反応標識(レピーターともいう)を確認することが大半です。この標識は、設置されている番線の出発信号機(あるいは閉塞信号機)の現示と対応していて、列車が出発できる状況であれば点灯するようになっています。

▲直江津駅の出発反応標識。妙高はねうまライン、日本海ひすいラインのどちらに進出するかに応じて、2つある標識のうち片方が点灯する。
なお、ドアを閉める(=出発する)際に駅員から「出発指示合図」や「乗降終了合図」が出される場合があります。前者は列車を発車させる合図、後者は旅客の状況が終了し車掌がドアを閉めて列車を発車させて良いことを示す合図です。これらの合図が出される駅では車掌はこれらに従います。

▲東京駅(総武地下ホーム)の出発指示合図器。なお、出発指示合図器、乗降終了合図器共々、会社、線区に応じて様々な形があるため、見比べてみるのも面白いだろう。なお、近年は出発指示合図器は使用が停止されているケースが多くみられる。
上記のような何らかの手段で出発できることを確認した車掌は、いよいよドアを閉めます。その際扱うのが下記のような「ドアスイッチ」です。ロッドを操作するタイプや、ボタンで操作するタイプなどもあります。「再開閉ボタン」は、閉まり切っていないドアのみを開ける働きをします。これは「ドアを閉めたけれど、1箇所モノが挟まってしまった」というような場合に有用です。



▲上:銚子電鉄3000系のロッド操作タイプのドアスイッチ(直接制御)中:ひたちなか海浜鉄道キハ11のボタン操作タイプのドアスイッチ(間接制御)下:キハE130系のドアスイッチに設置されている再開閉ボタン。
その後、ドアが閉まり、車側灯(列車の側面に設置されていて、ドアが閉まると消灯するもの)の滅灯、および旅客の接近がないかなど、ホーム上の安全を確認して、車掌は出発合図を送ります。つまり、車掌が乗務する電車列車・気動車列車においては車掌が列車の出発を司っていることになります。この際、通常は運転台に設置されている連絡ブザーにより車掌が運転士に出発してよいことを知らせます。もっとも、一部事業者では知らせ灯発車方式と呼ばれるような、運転士が「知らせ灯」と呼ばれる列車のドアがすべて閉まると点灯するランプを確認して列車を起動させる方式が採られていたり、機関車列車では異なる取り扱いがなされていたりしますので、必ずしもこの方式で列車が発車するわけではありません。

▲E127系の車側灯。ドアが開いているときに点灯する。なお、撮影時は半自動ドア扱い、すなわち乗客が自由にドアを開閉できる状態にあり、すべてのドアは閉まっているものの開扉状態と等しいため車側灯は点灯している。
また、ドアを閉める際、そしてドアを閉めた後ホーム上の確認をする際に、必ずしも車掌がホーム全体を見渡すことができるわけではありません。そのため、駅によってはホーム上に「ITV」という監視モニターが設置されていることがあります。

▲三鷹駅5番線のITV
出発合図を送ったのち、列車が発車する際には、車掌は乗務員室の扉の窓(『落とし窓』などと呼ばれることも)を開けて側面を監視します。その際、異常があった場合には直ちに列車を止められるよう、非常ブレーキに手をかけるようになっています。この車掌用の非常ブレーキは、古くは動作によって直接ブレーキ管を減圧し非常ブレーキをかける構造のものとなっていましたが、近時は電気的に非常ブレーキ信号を送るような仕組みになっているものが多いようです。


▲上写真:上信電鉄700形の車掌用非常弁(直接ブレーキ管を減圧するタイプ、所謂「赤玉」)。下写真:京王8000系(京王れーるランド保存車)の車掌用非常ブレーキ(電気的に非常ブレーキの信号を送るタイプ)。
列車がホームを出ると、車掌は後方を確認したのち、自動放送が搭載されていない車両の場合(あるいは、搭載されていても特段の必要がある場合)には放送を行います。
■駅間はどうしているのか
駅間で車掌は車内の巡視を行ったり、客室内で乗車券等を販売したりすることが多いのではないでしょうか。特急列車や無人駅が多い線区の場合は、車内改札を行うこともあるでしょう。
通過駅のある列車では、駅通過時に落とし窓から顔を出すか、あるいは後部運転台から列車の後方を注視して、通過する駅の安全を確認します。
■到着時の動きは?
列車が駅に近づくと、自動放送が設置されていない場合は次駅の案内を行います。また、自動放送が設置されていない車両はもちろん、設置されている車両でも、乗換案内を行う場合もあります。
また駅到着前、一部の私鉄線においては、車両がブザーにより運転士に停車合図を送る場合があります。到着時も、車掌は落とし窓から顔を出し側面の状態を監視するとともに、異常時に直ちに停車することができるよう、非常ブレーキに手をかけています。
このように、おおむね出発時と同様ですが、到着時には、車掌において速度・位置からして列車が所定位置に停車できるかどうかということも車掌は考えなければなりませんので、厳密にいえば出発時と全く同一ではありません。
列車が停車したら、車掌は車掌用の停止位置目標で列車が所定位置に停車しているかを確認します。所定位置から外れた場合、列車は退行あるいは前進して所定位置まで戻ります(もっとも、所定位置から大きく外れて列車が停止したがホームにはかかっている場合の取り扱いは、各事業者やそのケース等によって取扱いに差はあります)。なお、列車前方がホームに差し掛かっていないのにも関わらず扉を開扉してしまうことを避けるため、ホームには「後部限界表示」というものが備えられていることがあり、これは「この表示を列車の最後部が通り過ぎていなければ、列車はホームに収まっている」という意味を示します。

▲原ノ町駅の車掌用停止位置目標。画像のように、車両や両数によって停止位置が指定される場合もある。

▲新宿駅7番線の車掌用停止位置目標。12両編成の列車が走り始めて以来、従来のもの(画像左側)に加えて新しいタイプ(画像右側)のものも用いられるようになった。

▲三鷹駅5番線の後部限界表示。中央快速線のグリーン車組み込みに伴う12両用のものであるため真新しい。
また、豪雪地帯ではこのようなホーム上に張り付けるタイプのものでは冬季に機能しなくなるため、少し高い位置に設置される場合があります。
列車が所定位置に停車したことを確認したのちは、前述のドアスイッチを扱い、扉を開けます。
■停車中は何をしている?
車内外に取り付けられたスピーカーを使って、列車の行き先、種別、発車時刻などを案内することも多いのではないでしょうか。また、退避駅の場合などは、通過する、あるいは接続する列車の接近を監視したり、会社によってはスピーカーで駅構内の放送を行ったりする場合があります。
また、列車が長時間の停車をする場合で、特に夏季・冬季のように空調の実効性を確保する必要がある場合には、ドアの一部を閉める取り扱いや半自動ドア扱いを行う場合もあります。

▲新潟駅停車中の白新線の列車。半自動扱いが実施されており、乗客はボタンを押して列車に乗り込む。
以上のように、車掌は鉄道の安全運行を担うべくたくさんの業務を行っています。今後、車掌の乗務はワンマン化などで数を減らしていくと思われるため、いつかあまり見ることのできない存在になっていくのかもしれません。これを機に、日々列車に乗車する際、車掌の業務というものを改めて意識してみてはいかがでしょうか。