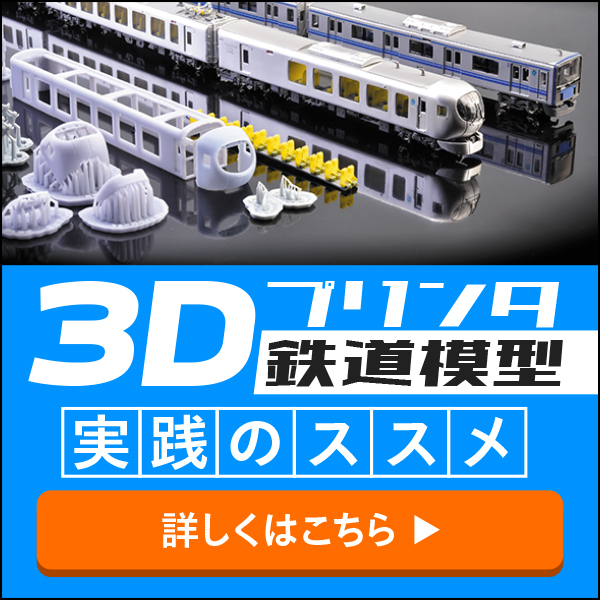text & photo:なゆほ
60年以上の歴史があるプラレールの製品・歴史・情報をまとめ、自身のホームページ「プラレール資料館」で公開しているプラレールコレクター なゆほさん の鉄ホビ連載!長い歴史を持つプラレールというおもちゃをコアな目線から語っていただきます!今回はプラレールで登場した「緑色のラッピング」車両たちをピックアップ。ここ十数年、意外と多かった緑をベースにしたラッピング車。見た目としても映える車両たちということで、それらは積極的にプラレール製品化されました。(編集部)
ステンレス製の鉄道車両が日本国内で走るようになってから65年以上が経ちました。セミステンレス車も含めれば、初期の国鉄サロ153形900番代、東急5200系・6000系・7000系や、南海6000系のようなほぼ無装飾で銀一色の車体に始まり、編成ごとに7色に色分けしたFRPを先頭部に採用した京王3000系、ドアを青く塗った横浜市営地下鉄1000形、側面窓周りに着色フィルムを用いた北総7000形や近鉄3000系、そして今でも多く見られる窓下に帯を入れてラインカラーやコーポレートカラーを表している車両たちなど、技術の発展や価値観の変化などにより、その外見も時代によって大きく変化してきています。
ステンレス車が普及した反面、首都圏では以前の単色や数色塗りが主流だった鋼製車体の電車は既に過去のものとなりつつあります。2000年代以降、銀色が目立つステンレスの車体にフルラッピングを施す事例が多く見られるようになりました。元々は車体広告のためのラッピングでしたが、車体全部に施せることが可能なのを応用し、過去の車両のデザインを復刻したものも見られるようになっています。
今回はそのステンレス車に施された過去の車両モチーフのラッピングのうち、プラレールで製品化された緑一色のラッピング車両をご紹介します。

▲緑色ラッピングのステンレス電車3種。
最初に製品化されたのは「E231系みどりの山手線」です。当時展開していた「たのしい列車シリーズ」の一つとして、2013年4月に発売されました。
103系電車が誕生して50周年を迎えたことを記念して2013年1月16日から12月28日まで運行されていたラッピングで、前面には103系のさよなら運転時に取り付けられていたヘッドマークを模した王冠型のサインが、側面には103系誕生50周年を記念するロゴが貼られていました。ラッピング期間中はお茶や道案内アプリ、そして「リラックマ」が追加で貼られるなど、いくつかのバリエーションがありましたが、このうち「リラックマ」は2013年12月に「リラックマみどりの山手線ラッピングトレイン」としてプラレール化されています。同一のラッピング車が2度も製品化された珍しい例です。
2つ目は「京王8000系高尾山トレイン」は京王電鉄の限定品です。2016年10月10日に発売されました。実車は2015年9月30日より現在まで運行されています。
現在の京王のイメージカラーであるアイボリーを纏って登場した初代5000系以前の車両である、2000系や2600系などの旧型車のカラーリングと、世界有数の登山客数を誇る観光地「高尾山」の緑をイメージしたラッピング車両です。
側面には山のイラストと「高尾山 Mt.Takao」の文字が入れられ、復刻カラーリングと観光地アピールを両立しています。側面は窓枠を除いて全てラッピングされているため、遠目に見ると全塗装車のように見えなくもないという、ステンレス車ラッピングの例の中では比較的珍しい形態を持ちます。
3つ目は「東急電鉄 東横線ラッピング電車(青ガエル)」です。こちらは東急電鉄の限定品です。つい先日の2025年2月3日に発売されました。東急東横線の開通90周年を記念し、2017年9月4日から運行されています。当初は2018年8月31日まで運行の予定でしたが、好評につき2025年現在まで継続中です。
通称「青ガエル」として知られる初代5000系の塗装をイメージしたもので、京王のグリーンよりは深い色合いになっています。モノコック車体である5000系特有の外板の補強材は明るい緑色のラインで表現されています。
通常流通品1種と事業者限定品2種、それぞれでプラレールに落とし込む際のデフォルメが異なるのが面白い点です。詳しく見ていきましょう。
▲黄緑6号、京王グリーン、東急グリーン。同じ緑色でも大きく印象が異なる3色だ。
3種とも成型色は緑色です。ステンレス部や屋根部は塗装で表現されていますが、ここに各車両のデフォルメへのこだわりが見えてきます。
「みどりの山手線」「青ガエル」はドア枠と窓枠が銀色に塗られ、ステンレス地の色を表現しています。後者は妻面まで銀色で塗装されており、前面と側面のみをラッピングする実車通りの形態をしています。車端部には連結面を示す黄色いテープまでもが表現されており、事業者限定品の中ではかなりの高グレードです。「みどりの山手線」の前面の帯と側面のロゴはステッカーです。
「高尾山トレイン」は、実車が妻面と窓枠を除いてステンレス地をあまり出していないのを反映してか、塗り分けは省略されて緑一色の車体となっています。屋根とクーラーキセの塗り分けがアクセントになっていますが、これは京王8000系の金型のクーラーが別パーツとなっているためできる技だと言えます。京王8000系は前面部とスカートが同じ色に塗られているため、高尾山トレインでも同様にラッピングの色が施されています。プラレールでは連結器周辺をライトグレーで塗り、特徴的なブラックフェイスと共にデフォルメ上のアクセントになっています。側面の文字とイラストは印刷で表現されています。
「青ガエル」は前述した特徴に加え、実車でも目立っている車両番号と「T.K.K.」の3文字を忠実に再現しています。東急のラッピングはスカートまで及ばないため、他の5000系と同様のグレーで塗られています。
このように比較してみると、実車の特徴的な部分を取捨選択してデフォルメされているプラレールとは言え、こういったラッピング車両に限っては特にこだわりを持ってデザインされているのが分かります。
以前展開されていた、ラッピング車のみを製品化するシリーズだった「SCシリーズ」や、事業者限定品でも「京王サンリオピューロランドラッピングトレイン」「京阪きかんしゃトーマス号」「ラッピング江ノ電 1000形義経号」など、フルラッピングの車両を製品化した例は多く存在しますが、それぞれ異なる会社で異なる車両をモデルとしつつも、近いカラーリングのものが製品化されたのはこの3種類のみです。京王も東急も山手線に接続する路線の一つ、そして戦時中は経営統合されていた会社です。
それぞれ企画元が異なるため、プラレールで揃ったのは偶然と考えられますが、どこかに縁を感じてしまいます。