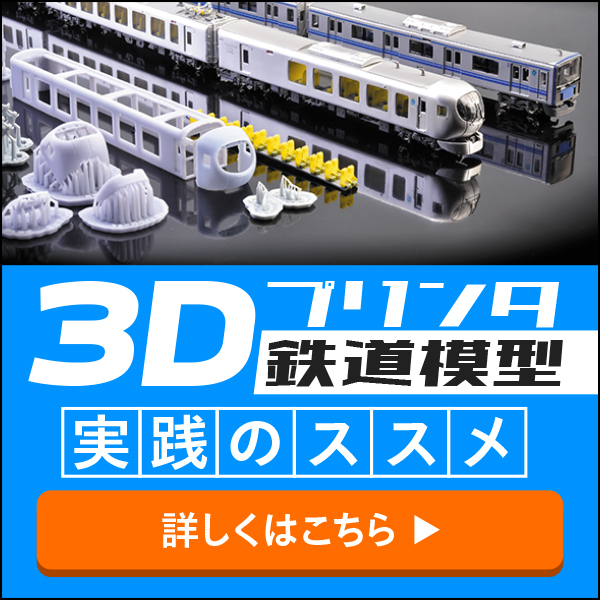text & photo:なゆほ
60年以上の歴史があるプラレールの製品・歴史・情報をまとめ、自身のホームページ「プラレール資料館」で公開しているプラレールコレクター なゆほさん の鉄ホビ連載!長い歴史を持つプラレールというおもちゃをコアな目線から語っていただきます!今回は限定品として発売された209系にクローズアップ!ぱっと見、至って普通に見えますが、よく見ると変わったところがチラホラ…。なぜこのような不思議な形態になっていったのでしょうか?その謎に迫ります。(編集部)
【写真】205系みたい?プラレールの中央・総武線209系を写真でよく見る!
1992年、JR東日本が画期的な新型車両を開発しました。それが2025年現在に至るまで、JRに限らず私鉄でも同様の設計思想を持つ車両が生まれるきっかけとなった901系、後の209系です。1993年から量産車の本格配置が始まり、京浜東北線と南武線、八高線などに投入されました。
拡幅車体の500番代や、後のE231系試作車となる950番代、地下鉄乗り入れ用の1000番代を始め、多くのバリエーションが存在しています。後継となるE231系・E233系・E235系の登場により活躍の場を狭め、全盛期と比較すると大幅にその数を減らしている209系ですが、房総地区・八高線・京葉線・武蔵野線ではまだ現役です。さらに試験車に転用されたMUE-Trainや、観光列車「B.B.BASE」、伊豆急行に譲渡された「3000系」など、21世紀の通勤電車の礎を築いた電車は今でも活躍を続けています。
国鉄分割民営化からまだそれほど経っていない時期に登場した209系は鉄道玩具界にも大きな印象を与え、プラレールでも1993年に「人形あそび通勤電車」としてデビューを果たしました。しかし、当初の発売形態の影響により、後に発売されたものに少々変わったバリエーションが生まれてしまいました。
▲2000年10月14日に発売された「209系通勤形直流電車」。顔は209系だが、車体をよく見ると…?
209系量産車のデビューと同年の1993年、プラレールの新シリーズ「人形あそび」が登場しました。「通勤電車」「のぞみ号」「D-51蒸気機関車」の3種類が発売され、前2つは先頭車と後尾車に、D51は炭水車と客車に付属の人形を乗せて遊ぶことができました。
「通勤電車」「のぞみ号」は中間車に電池ボックスと搭載して先頭車のモーターと繋げる構造で、2両永久連結の形態を持ちます。人形を乗せるため、屋根には大きな穴が開けられており、既存の型がある300系ではパンタグラフ無しの車両とすることで差別化を図っていますが、初登場の「通勤電車」に関しては完全新規制作の車体だったため、当初から先頭車・後尾車の屋根に穴が空き、中間車は電池ボックス対応、さらに先頭車のクーラーは車端部に寄っているという特殊な仕様でした。
新型の通勤電車をモデルとしたのはいいものの、「のぞみ号」「D-51蒸気機関車」と比較すると実車同様の銀色の車体ではインパクトが弱いと判断されたのか、オレンジ色にエメラルドグリーンの帯を巻いた架空の姿とされています。
こうして「人形あそび」専用の型として登場した209系。通常仕様に変更しようとすると手間がかかってしまうためか、京浜東北線の103系が全て置き換えられた1998年3月以降になっても「209系」としてプラレールで製品化される事はありませんでした。
▲側面だけ見るとほとんどカナリア帯の205系だ。
同年12月、拡幅車体の500番代が中央・総武線に投入され、新たなバリエーションが加わります。新たに登場した首都圏JRの電車ということで、もちろんプラレールでは製品化したかったところでしょうが、前述の通り、まだ車体の型がありません。
そんな中、2000年10月14日に開催された鉄道フェスティバルに出展したメーカーブースで、中央・総武線209系が発売される事となりました。ですが、その姿はあまりにも意外なものでした。「人形あそび通勤電車」の前面を「近郊電車」や205系「通勤電車」の車体に取り付けたものだったのです。
同様の手法で別形式を表現したものは2000年代初頭に多く存在し、京王8000系(2000年4月)や東急目黒線3000系・営団南北線9000系・都営三田線6300形(2001年9月)、小田急2000形(2003年4月)などの例がありますが、この「209系通勤形直流電車」は、車体とセットで開発されたはずの前面パーツを既存の別形式のものと合わせて表現しているという点が特筆できます。
おそらく、本来の金型の改修がまだ行われていなかったのに加え、事業者限定品でも前面パーツの交換だけでそれらしく見えてしまい、さらにどれも売れ行きが良かったという状況がこのような製品を生んだものだと思われます。
総武線をベースとしていることからも分かるように、モデルは209系500番代です。前面をよく見ると、窓と帯の間が塗られておらず、0番代のブラックフェイスとは差別化を図っている様子が分かりますが、それでも顔はどう見ても0番代なのがご愛嬌です。
屋根は車体の成型色をそのまま使った薄いグレーで、新形式電車であることを表すと同時に、前年に発売された「通勤電車(カナリア)」と被らないように配慮がなされています。
翌2001年のプラレール博にてカラーバリエーションとして「209系通勤形直流電車(スカイブルー)」が発売されました。こちらは本来の0番代をモデルとしていますが、やはり車体は「近郊電車」あるいは「通勤電車」のもの。「人形あそび通勤電車」の車体が正しく使われるまではもう少し時間がかかりました。
2002年3月、とうとう「人形あそび通勤電車」の車体が通常仕様の3両編成として初めて発売されました。それが「E217系横須賀線」です。意外にも本来の209系ではなく、同一の設計思想を基に開発された近郊型のE217系としてのデビューでした。このE217系は中間車に「プラキッズ」を乗せられる仕様となり、改修後もある種「人形あそび」が出来る車体として再出発したことが興味深いところです。
こうして、本来JR東日本の209系として作られたはずの車体はその後も様々な電車に流用される事になります。JR東日本E217系・E231系・E233系・E501系・E531系、JR東海313系、JR西日本207系・223系・321系、JR九州811系・813系、西鉄3000形と、本来の209系を含めて13形式の車体として使われたことにより、一部のファンの間では「汎用金型」と呼ばれているという話もあります。中間車は先述のプラキッズ対応をはじめ、サウンド車と通常のトレーラー仕様という3種類が存在しているのも「汎用」と呼ばれる所以かもしれません。
しかし、開発当初の「209系」として単品で発売されるにはタイミング遅すぎたためか叶わず、改めて発売されるのは2006年3月の「京浜東北線スペシャルセット」まで待たねばなりませんでした。とはいえ、2003年にほぼ同じ車体を持つ「サウンドE501系常磐線」が品番付きの通常品として発売されたことにより、一応は本来の前面パーツと車体の組み合わせで世に出たことになります。
209系0番代が京浜東北線から引退して、2025年1月で15年。最初に投入された線区の京浜東北線仕様としてはプラレールで定着する事はありませんでしたが、209系から始まった「通勤・近郊電車の標準仕様」という指針は、実車同様にプラレールでも脈々と受け継がれています。