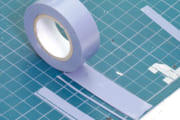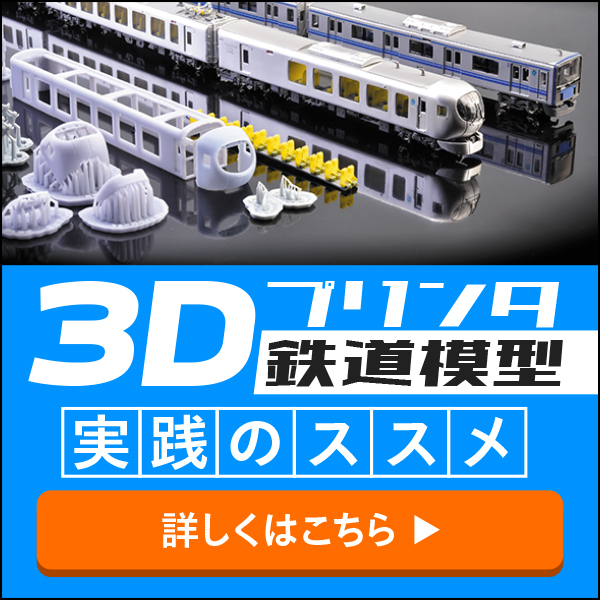1980年代当時の当時のロマンスカーを代表した形式である7000形LSEと10000形HiSE。今回はこの2形式のディテールアップ作例を紹介しようと思う。


■複雑な連接構造を再現した画期的な現行仕様製品
1980年代の小田急沿線に住む少年たちの憧れの的だったロマンスカーの製品たちは、改良を続けながら今なお販売され続けているロングセラーだ。Nゲージ製品では、7000形LSEの実車登場後間もない1981(昭和56)年にTOMIXから製品化。まだ日本型Nゲージ黎明期ともいえる時期に、実車の連接構造まで忠実に再現された画期的な製品が登場した。2000年代以降は追随するようにバリエーションが展開され、ほぼすべての仕様が製品化されている。


■塗装・部品取付・部品加工でロマンスカーを細密化!
今回作例のベースにしたのは、7000形LSEは復活旧塗装・ブランドマーク付の7003F(品番92894)と10000形HiSEはロゴマーク付(10001F)をベースに加工(品番92845の旧製品)した。
以下ギャラリー画像にて、7000形LSE/10000形HiSE共通の加工ポイントの他、それぞれの車種の加工ポイントを解説したものをまとめたのでご覧いただきたい。
■7000形LSE/10000形HiSE共通加工ポイント
- 車体はMr.スーパークリアー光沢で塗装。写真のようにニコイチに組んで塗装した。妻面がない連接構造だからできるワザだ。
- 屋根は小田急特有の白に近いライトグレーで塗装した後、中央付近をエアブラシでダークグレーにウェザリング。
- さらに屋根全体にエナメル塗料のつや消しブラックを塗り、半乾き時に溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取りディテールを強調。
- 屋根と同様に車体のドア付近もエナメル塗料でスミ入れ。
- パンタグラフはプライマー処理後、シルバーで塗装。その上からエアブラシで集電舟付近にダークグレーを吹き付けてウェザリング。
- 車内座席はヘッドカバーを白でタッチアップ。展望席はライトユニットの都合で床が高いのでつや消し黒で塗装。先端はレッドブラウンで塗装。
- ヘッドライトは白色となるので、チップLEDの表面全体をクリアーオレンジに着色して電球色化した。
- 導光材兼用のライトカバーは非点灯時に内部が黒く見えるので断面を白で着色。
- 旧製品ゆえ、製品によっては残ったバリで隙間ができ、光漏れが生じる場合がある、
- また遮光のため、装着時に配線用の黒のビニールテープで天面を覆っておく。
- 7000形の室内灯取付状態。7000形は車体長が短いので、プリズムを半分にカットしてから使う。
- 10000形は側面の愛称表示を点灯させるため、光源がプリズム中央にあるマイクロエース製を使用。
- 運転台内部はつや消し黒で塗装。椅子は赤系で着色。ジオコレの乗務員を胸元でカットしたものを接着した。
- 10000形の運転席パーツの側面下部が、点灯化する愛称表示窓を塞いでしまうので、該当部分をカット。
- カーテンの表現にはテープを使用。最近雑貨として人気のカラーマスキングテープが便利。
- 作例は青系のものを使用したが、室内灯非点灯時でも効果アリ!
- 実車の10000形展望席側面窓のピラーは、内側が太くなっている(表側は黒色処理)。作例では1.5mm幅に切った黒色のテープを貼り表現。
- 今回はテープが大活躍だが、グレーのビニールテープで外周幌を表現してみようと思う。
- 幌表現のある台車側はカットしたビニールテープの帯材を妻面に沿って元の幌に巻き付ける。
- フック側には同じ帯材にのりしろとなる2mm幅の帯材を追加したものを車体内側へ巻き付けるように貼る。
- 元の幌には黒のビニールテープを貼って内側の幌を表現。
■7000形LSE加工ポイント
- 展望室及び運転室内の加工は窓が大きいのでその効果は高い。
- 屋根上はウォッシングとスミ入れによりディテールを強調。
- パンタグラフは登場時は菱形を搭載していたが、2005年頃からシングルアーム式に換装された。作例では配管を着色、スミ入れを施すことで立体感を出した。
- 未加工の先頭車を横から見る。先頭部の台車がやや「ウイリー」しているのがわかる。
- 台車の首振り機構にある突起を0.8mm、集電スプリングも3段ほどカットして車高を調整。写真は施工後。
- 愛称表示は窓側を薄めたライトグレーで塗装し、自作したクリアーステッカーを貼って幕らしさを表現した。
- ヘッド・テールライトおよび室内灯の点灯状態を見る。やはり展望席が暗いのと一体で点灯するテールライトの改良が今後の課題。
■10000形HiSE加工ポイント
- 乗客を配置した展望席。初期車(10002Fまで)特有の赤青交互配置の座席も着色表現。
- 屋根上はウォッシングとスミ入れによりディテールを強調。ちなみに屋根上のキセは換気用で、冷房装置は床下にある。
- パンタは下枠交差式。配管を着色しスミ入れを施してある。
- 先頭車側面に付く愛称表示幕。室内灯を光源として点灯化している。Φ0.5のピンバイスで窓周囲に穴をあけた。
- その後カッターで開口。
- そこにt0.5のプラ板をはめ込んだ。表示は自作ステッカーである。
- 4号車(手前)には公衆電話用のアンテナと8号車(奥)には台座のみを追加表現。パーツはGMキットの余剰品からだ。
- ヘッドライトと室内灯の点灯状態を見る。やはり点灯化した幕が効果的だ。
この記事は「小田急電鉄完全ガイド」に掲載されている内容を一部抜粋しています。小田急車両のNゲージの細密加工記事の他、華やかなロマンスカーや地域の足となっている通勤電車まで幅広くカタログ形式で紹介。さらに引退した往年の車両や、縁の下の力持ちの検測車まで、様々な車両にクローズアップする小田急ファン必携の一冊です。